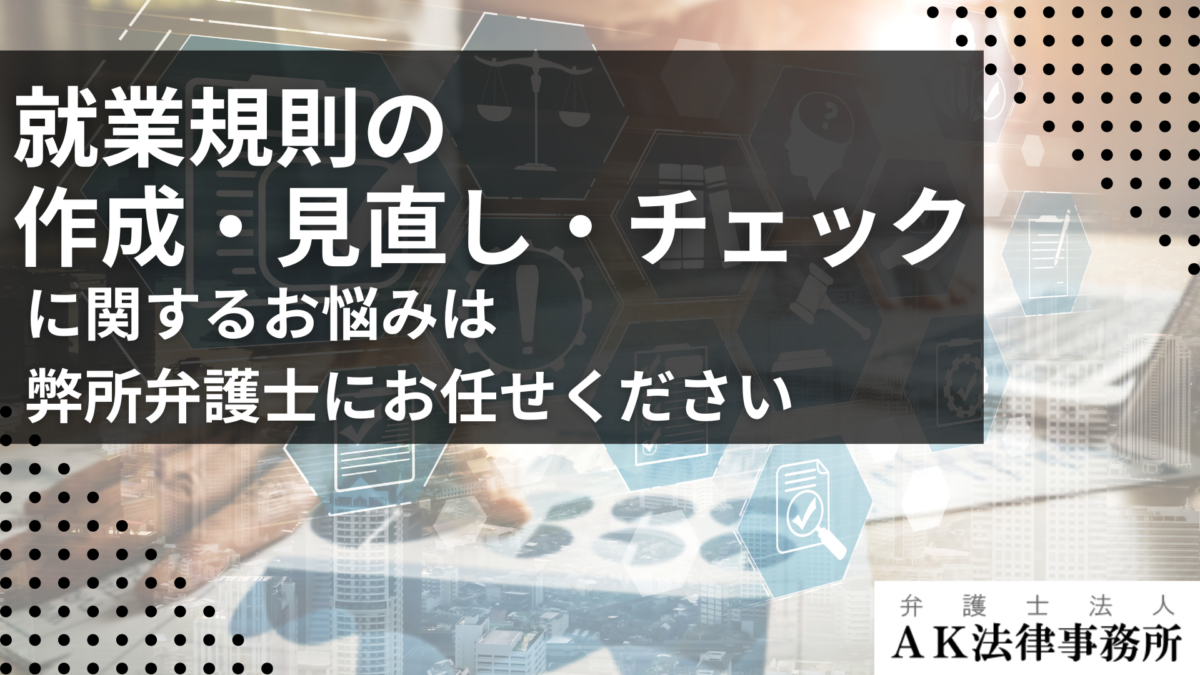企業経営において、就業規則は従業員との信頼関係を築く重要な土台です。しかし、就業規則の作成や見直しは難易度が高く、経営者の方々の中には「どのように作成すれば良いのか」「リスクをどのように防げるのか」といった悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。
就業規則とは?
就業規則とは、企業と従業員の間で守るべきルールを定めた文書です。
就業規則は、労働時間や賃金、休暇制度、懲戒処分といった重要事項を規定し、労働環境の透明性を高める役割を果たします。適切な就業規則がない場合、従業員とのトラブルが発生しやすくなるため、企業にとって極めて重要な文書です。
就業規則が適切に運用されている企業では、従業員が安心して働ける環境が整い、生産性の向上にもつながります。一方、未整備の場合には、トラブルが頻発し、企業のイメージや信頼性が損なわれるリスクが高まるため、就業規則の作成は経営者にとって欠かせない課題といえます。
就業規則に関するよくあるご相談・トラブル
企業の就業規則に関して、よくご相談いただくものや、トラブルについて弁護士からご説明いたします。
労働条件の不明確さ
労働条件が曖昧なままでは、従業員が自らの権利を正しく理解できず、結果として労使間での摩擦が生じやすくなります。残業手当や休暇制度について明確な記載がない場合、従業員が不満を抱き、トラブルとなるケースも少なくありません。労働条件を明確に定めることは、従業員の安心感を高めるだけでなく、企業の信頼性向上にもつながります。
法改正への対応不足
労働関連法は頻繁に改正されるため、これに対応して就業規則を見直さなければなりません。法改正に対応していない規則を運用すると、知らない間に法令違反に該当し、罰則を受ける可能性があります。例えば、育児・介護休業法の改正に伴い、新たな規定を就業規則に反映させることが求められるケースが増えています。法改正に敏感であることは、リスクを回避するために重要です。
懲戒規定の不備
従業員に対する懲戒処分を適切に行うためには、具体的で明確な懲戒規定が必要です。しかし、懲戒規定が不十分であったり曖昧な表現が多い場合、従業員から不当解雇として訴えられるリスクがあります。例えば、遅刻や欠勤に対する処分が不明確だと、従業員が処分に納得せず、紛争に発展する可能性があります。
経営者の中には、従業員とのトラブルが起こるたびに対応することで負担を感じる方も多いのではないでしょうか。こうした問題は、就業規則を適切に整備し、運用することで未然に防ぐことが可能です。
就業規則を作成する理由
就業規則は、企業の内部統制を整え、従業員との信頼関係を構築する上で欠かせないツールです。また、法令遵守を確保し、労務・就業トラブルの未然防止にもつながるため、適切な作成が求められます。
就業規則の作成は義務?
労働基準法第89条では、常時10人以上の労働者を雇用する事業場に対して、就業規則の作成と労働基準監督署への届出を義務付けています。この義務を果たさない場合、罰則が科される可能性があります。また、従業員数が10人未満であっても、就業規則を整備することで労働環境の明確化やトラブル防止につながります。
義務である以上、企業側が法令を遵守することは当然ですが、それだけでなく、就業規則は経営者が従業員に対して透明性の高い労働条件を示す重要な手段でもあります。明確なルールを定めることで、企業と従業員が相互に信頼を深め、健全な労働関係を築くことが可能になります
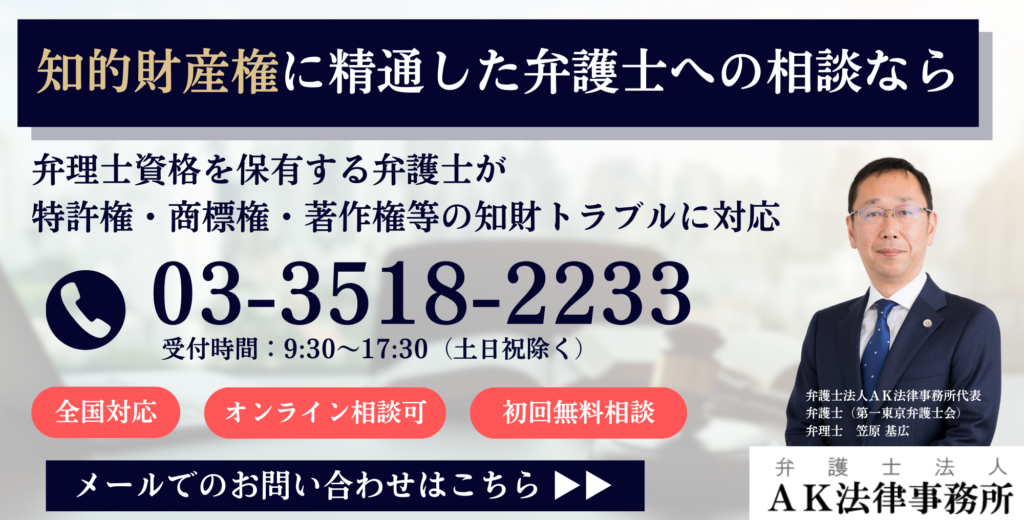
就業規則に記載すべき事項
就業規則に記載すべき事項は、大きく以下の3つに分かれます。
絶対的必要記載事項
労働条件や賃金、労働時間など、必ず記載が求められる事項。
相対的必要記載事項
賞与や退職金制度など、導入している場合に記載が求められる事項。
任意的記載事項
福利厚生や社内ルールなど、企業独自の規定。
これらを網羅的に記載することで、従業員が規則を理解しやすくなり、労働環境の透明性を高めることができます。また、リスクを防ぐためには、記載内容が法令に準拠していることが不可欠です。
就業規則を作成する際の注意点
就業規則を作成する際の注意点は、労務トラブルや最新の法令を理解していない場合、なかなか理解することが難しいポイントです。
法令の遵守
就業規則は関連法令に従う必要があります。特に法改正に即して更新を怠ると、罰則や信頼性の低下につながるリスクがあります。最新の法令に対応することが重要です。
企業の実態に即した内容にする
企業の実態に即した内容にすることが求められます。業界特有のルールや従業員の働き方に応じた規則を整備することで、実効性が高まります。
定期的な見直し
事業環境や法改正に合わせて規則を更新することが必要です。これにより、労務トラブルを予防し、適法な運営を確保できます。
就業規則を作成する際には、従業員との話し合いや意見収集も重要です。これにより、規則が現場で実際に運用しやすいものになり、従業員の理解と納得を得ることができます。
ひな形の使用における注意点
ネット上で配布されている就業規則のひな形は便利なツールですが、そのまま使用することには多くのリスクが伴います。
まず、ひな形は個々の企業の実態を反映していない場合がほとんどです。例えば、業界特有の規制や働き方、労働時間の取り決めなどが反映されていないと、従業員からの疑問や不満が生じる可能性があります。
また、ひな形の内容が最新の法改正に対応していない場合もあり、そのまま使用すると法令違反となるリスクもあります。特に、労働基準法や男女雇用機会均等法などの改正が頻繁に行われているため、規則が古いままだとトラブルにつながる可能性が高くなります。
ひな形を使用時のよくあるトラブル
市販のひな形を使用する場合、以下のようなトラブルが発生しやすいです。
法改正に対応していない
企業独自の事情が反映されていない
曖昧な表現が多く、解釈に誤解を生じる
特に中小企業においては、「コスト削減のためにひな形を利用したが、結果的にトラブルが発生し、余計な費用がかかった」というケースが少なくありません。適切なサポートを受けることが、こうしたリスクを回避する鍵となります。
就業規則作成を弁護士に依頼するメリット
就業規則作成は企業の中だけで作成した場合、前述のようなリスクを負う可能性が高くなってしまいます。
このようなリスクを避けるため、弁護士に依頼するにしても、企業にどのようなメリットがあるかわかりにくいかと思います。
以下に依頼するメリットをまとめていますので、ぜひご覧ください。
企業の実態に即した内容にすることができる
弁護士に依頼することで、企業の業種や規模に合わせた就業規則を作成できます。例えば、飲食業やIT業界など特有の働き方に対応した規則を設けることが可能です。
紛争リスクを最小限に抑えられる
就業規則の不備は、従業員とのトラブルの温床になります。弁護士は専門知識を活用し、労使双方にとって公正な規則を作成することで、紛争リスクを軽減します。
紛争発生時の対応を迅速に行うことが可能
万が一紛争が発生した場合でも、弁護士が作成した就業規則があることで、迅速かつ的確な対応が可能となります。
就業規則における当事務所のサポート
弁護士法人AK法律事務所では、就業規則の作成・見直し・リーガルチェックを通じて、従業員の就業における法務体制を強化します。法改正や最新の労働問題に精通した弁護士が、企業ごとの事情に即したサポートを提供します。
弁護士費用
詳細はお問い合わせください
| サポート内容 | 費用 |
|---|---|
| 初回相談 | 無料 |
| 顧問契約 | 5万円/10万円/15万円 |
| 経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 300万円以下の部分 | 8% | 16% |
| 300万円を超え、3000万円以下の部分 | 5% | 10% |
| 3000万円を超え、3億円以下の部分 | 3% | 6% |
| 3億円を越える部分 | 2% | 4% |
顧問弁護士費用(税別)

就業規則の作成やチェック、見直しに関する問題は当事務所にご相談ください
弁護士法人AK法律事務所では、企業での実務経験のある弁護士が、企業の就業規則に関する課題を包括的にサポートしています。作成・チェック・見直しの各フェーズにおいて、専門的な観点からアドバイスを提供し、企業のリスクを最小限に抑えるお手伝いをいたします。詳しくは当事務所弁護士までお問い合わせください。