1 特許権侵害とは
1.1 はじめに
特許権は、新規性・進歩性・産業上の利用可能性をはじめとする一定の要件を充足する発明に対して付与される権利です。特許権は所有権などの物権に類似しているともいわれる強力な権利で、特許発明を特許権者の許可なく無断で実施すると、損害賠償請求や実施差止め請求の対象 となるだけでなく、場合によっては 刑事罰が科されます。
しかし、企業が時間とコストをかけて開発した技術が、第三者に無断で使用されるケースは少なくありません。特許権侵害に気づいた際には、迅速かつ適切な対応が求められます。本記事では、特許権侵害を発見した場合の流れや対策について解説します。
1.2 特許権侵害とは?
特許権侵害とは、特許権者の許可なく、特許発明を業として実施する行為を指します。例えば、以下のような行為が該当します。
特許権侵害となる行為の例
- 特許発明を使用した製品の、無断製造、販売、輸出入
- そのような製品の、ecサイトやカタログへの掲載
- 製造方法の特許発明を用いて製造した製品の販売
- 特許発明を使用した装置やソフトウェアの使用
これらの行為が確認された場合、特許権者は法的措置を検討する必要があります。
1.3 特許権侵害の判断基準
特許権侵害を主張するには、以下の要件を慎重に確認する必要があります。
特許権侵害の要件
- 特許発明の技術的範囲に属するか(クレームチャートによる分析等)
- 業としての実施に該当するか(家庭内、個人的な実施では無いか)
- 特許権の有効性が維持されているか(特許料未納による失効、無効・取消等)
- 特許権侵害とならない事由がないか(先使用権、無効理由など)
詳細はこちらの記事をご覧下さい。
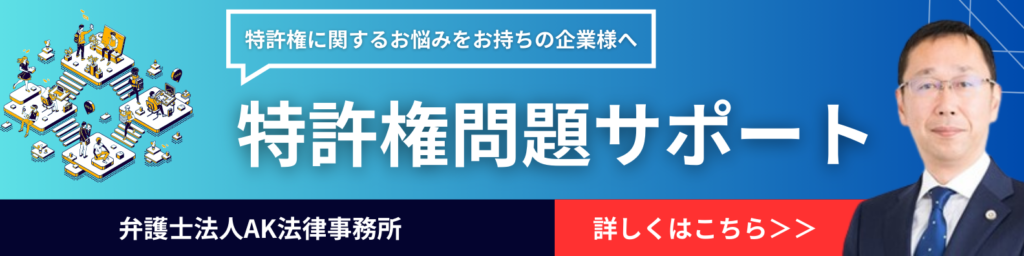
2 特許権侵害を発見した場合の対応フロー
大切な特許権が侵害されていることを発見した場合、どのような対応をすべきでしょうか。その流れを解説します。
2.1 事前準備
特許権侵害に対する対応をする前に、以下の点を準備します。
特許権の有効性確認
特許権侵害が発生するには、特許権が有効に存続していることが前提となります。
特許権者であれば当然知っているべきことですが、具体的には、特許権が特許料の未納等で消滅していないか、無効審判、異議申立て等で無効、取消しなどになっていないかを確認する必要があります。
なお、無効、異議等で遡及的に特許権が消滅していない限り、過去の侵害行為についても損害賠償請求は可能です。
被疑侵害物件、方法が、特許発明の技術的範囲に属するか精査
特許権を侵害していると考えられる人(被疑侵害者)が特許発明を実施していることが、特許権侵害の前提となります。クレームチャートを作成したりして、被疑侵害物件や方法が特許発明の技術的範囲に属するか否かを精査します。
証拠収集(製品カタログ、販売資料、サンプルの確保など)
侵害行為差止め、損害賠償請求等を訴訟外で請求するとしても、その後の法的手続きに堪えうる証拠を収集しておくことが重要です。
発明の内容によって収集すべき資料は異なります。次のような資料を収集することが考えられますが、ほんの一例に過ぎません。
収集すべき資料の例
- 製品サンプル(市販のものであれば購入し、レシート等を保存します)
- 製品仕様、図面、成分表示、添付書面
- 実施結果の写真等(建築物、土木工事等、購入できないものに関する発明の場合)
- カタログ
- ウェブサイトのプリントアウト(プリントアウト日付けが重要となることがあります)
- 販売資料(見積書、入札書類など)
- 製品分析資料(第三者機関による分析が望ましいです)
2.2 警告と訴訟外の交渉
事前準備が進み、法的手続きに移行しても堪えられる程度の資料が収集できた場合、侵害行為の停止や和解金の支払い、ライセンス契約の締結などを求めて、訴訟外で交渉を行い解決を図ることがあります。
警告書の送付
まず、相手方に警告書を送付し、侵害の事実を指摘して、実施行為の停止、損害賠償を請求したり、ライセンス(実施許諾契約)の申入れをします。なお、この時点で、製品の販売数といった損害賠償額の算定に必要な情報の開示を求めることもあります。
訴訟外の交渉
被疑侵害者が警告書の送付だけで製品の販売を停止したり、ライセンスに応じることもありますが、さほど多くはありません。
特許権侵害の成否について疑義がある場合に、互いに技術的なプレゼンテーションを行って主張を明らかにしていきます。また、ライセンスや和解金といった条件について協議をし、和解契約の締結に向けて交渉します。
訴訟外の交渉は有益か
法的手続きをする前に訴訟外で交渉することは必須ではありません。いきなり法的手続きをしても問題はありません。
訴訟外における交渉では裁判所のような判断権者がいないため、水掛け論になってしまい、決着がつかない場合があります。例えば、被疑侵害品が特許発明の技術的範囲に属するか否かについて、技術的、法的な議論を行ったあげくに、主張の対立が鮮明になっただけで終了することも珍しくありません。また、会社や担当者の面子の問題で、頑なに特許権侵害を認めたくない場合もあるでしょう。
そのため、訴訟外の交渉は無駄どころか、協議における主張によってこちらの手の内を知られるため有害であり、すぐに法的手続きをすべき、という考え方もあります。
3 特許権侵害に関する法的手続きの流れ
3.1 法的手続きの概要
特許権侵害に関する法的な手続きには次の表のようなものがあります。これらの手続きにはそれぞれ特徴があり、目的に適した手続きを選択することが重要です。
| 種類 | 法的手続機関 | 求める内容 |
|---|---|---|
| 特許権侵害訴訟 | 裁判所 | 侵害行為の差止め、損害賠償など多岐にわたる |
| 特許権侵害 | 裁判所 | 侵害行為の仮差止め |
| 輸出入差止申立て | 税関 | 侵害製品の輸出入の差止め |
| 刑事手続き | 所轄の警察署、検察庁 | 侵害者の刑事処分 |
| 判定請求 | 特許庁 | 特許権侵害の有無の判定 |
それぞれの手続きの特徴について、説明します。
3.2 特許権侵害訴訟(本案訴訟)
いわゆる特許裁判です。裁判所に訴えを提起し、以下のような請求を行います。
特許訴訟における請求
- 特許権侵害行為の停止(侵害製品の製造、販売等の停止)
- 損害賠償
- 不当利得返還
- 侵害予防措置(侵害品の廃棄等)
- 信用回復措置(謝罪広告など)
訴訟ですので、当事者は証拠に基づいた厳格な証明を求められます。また、上訴も可能ですし、必要な期間も長いです。よって、費用も高くなりがちです。
他方で、判決が確定すれば、損害賠償金の取立てなどの強制執行が可能となりますので、強力な手続きといえます。
まとめ-特許訴訟の特徴
- 証拠に基づいて立証
- 上訴可能
- 長期間かかる
- 費用が高い
- 強制執行可能
3.3 特許権侵害停止仮処分申立て
裁判所に対するもうひとつの手続きは、特許権侵害停止仮処分申立手続きです。民事保全法に基づいて、特許権侵害行為の停止を求める訴訟(上記の特許訴訟のこと。仮処分手続きに対し、「本案訴訟」といわれます)の判決がなされるまでの損害を防止するため、侵害行為を迅速に停止させる仮処分を申し立てる手続きです。侵害行為の差止め、廃棄請求などが可能ですが、損害賠償請求はできません。
仮の処分を求める手続きですので、本案訴訟で求められるような証拠に基づく厳格な証明までは求められず、裁判官が一応確からしいという程度の心証に至るため立証活動、すなわち疎明で足ります。
また、迅速な権利保護のための制度ですので審理期間が短いとも思われます。しかし、特許権に基づく仮差止は侵害者の不利益が大きいため、裁判所によってしっかりとした審理が行われます。よって、現実的にはさほど迅速ではありません。
審理の結果、差止めの仮処分が発令されてしまうと、執行停止の方法がないため権利者にとって有利となります。しかし、あくまでも仮処分ですので、差し止められた側は本案訴訟(上記の特許権侵害訴訟)で侵害の成否を争うことができます。仮処分で勝っても、本案訴訟で負けてしまうと特許権者が損害賠償をすることになってしまいますので、注意が必要です。
本案訴訟の差止め請求で裁判所に支払う訴訟印紙代は、経済的利益に応じて算出されます。例えば次の式で算定される額です。よって、本案訴訟で差止めをする場合の訴訟印紙代は場合によって高額になりがちです。
差止訴訟の訴訟印紙代
- 原告の訴え提起時の年間売上減少額×原告の訴え提起時の利益率×権利の残存年数×8分の1
- 被告の訴え提起時の年間売上推定額×被告の訴え提起時の推定利益率×権利の残存年数×8分の1
- (年間実施料相当額×権利の残存年数)-中間利息
他方で、仮処分の場合には一律2000円で済むというメリットもあります。
3.4 税関での輸出入差止申立て
特許権を侵害する貨物が輸出入される場合、税関長に対し、侵害品の輸出入を差し止め、認定手続を執るべきことを申し立てる制度です。税関は自主的に侵害品の輸入差止めをする場合もありますが、権利者の申立てによってこれを行う場合も多いです。
特許権者は、侵害品であることを疎明して申立てを行います。申立てのあった場合、税関は侵害品の認定手続きを行います。手続きにおいては、輸入者等の利害関係人も証拠を提出したり意見を述べることができます。
審査の際に利害関係者から意見書が提出された場合や、侵害の事実が疎明されているか否かの判断が困難である場合、弁護士・弁理士や有識者から選任される専門委員や特許庁長官に対して意見を求めたりします。また、特許権者や輸入者からの意見聴取の機会、すなわち、税関におけるプレゼンテーションの機会が設けられることもあります。このような手続きを経て、税関は特許権侵害の有無を判断します。
簡易、迅速、かつ無料の手続きです。しかし、税関が申立て人の疎明によって特許権侵害の有無を認定するため、司法手続き(訴訟、仮処分)のような厳格性には欠けます。
税関によって侵害品である旨の認定がされると、当該輸入貨物は輸入されず没収等となります。
3.5 刑事手続き
特許権侵害には、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金、あるいはこれらの両方が科されるという刑事罰があります。侵害の罪が成立するためには次の要件を満たすことが必要です。
特許権侵害の罪の成立要件
- 侵害者の故意による侵害行為によって特許権侵害の結果が発生していることなど(構成要件該当性)
- 侵害行為が違法であること(違法性)
- 行為者に責任があること(有責性)
特許権侵害罪は非親告罪ですので、特許権者の告訴がなくとも公訴提起が可能です。しかし、現実的には警察や検察庁に被害届や告発状(告訴状)を提出し、捜査の端緒とすることが多いです。特許権侵害の有無を判断するには、特許発明の技術的範囲の属否の解釈や、無効事由の有無といった判断をする必要がありますので、捜査機関に捜査を開始させるハードルは高いといえますし、特許犯罪で起訴までされるケースは希です。
3.6 判定
判定とは、特許庁が、被疑侵害物件が特許発明の技術的範囲に属するか否かを中立な立場で判断を示す制度です。
いわば公的な鑑定といえますが、特許庁の判定結果には拘束力がなく、特許権侵害訴訟手続でもそれなりに尊重されるかもしれませんが裁判所や当事者がこれに拘束されることはありません。
4 特許権侵害トラブルを弁護士に相談するメリット
4.1 侵害の有無を的確に判断
特許権侵害の成否を判断するためには、被疑侵害物件等の特許発明の技術的範囲への属否や均等論、さらに無効理由の有無といった様々な点を検討する必要があり、専門的な知識が必要となります。またそれだけではなく、特許権侵害とならない事由に該当していないことを検討する必要も生じます。
弁理士・弁護士のサポートによって適切な対応方針を決定することができます。
4.2 交渉対応
弁護士は、知財事件かどうかにかかわらず相手方と交渉することが多く、特許権侵害紛争についても同様です。
4.3 事業への影響を最小限に抑える
特許権侵害の問題が長引くと、企業の事業活動に悪影響を及ぼします。迅速な対応を行うことで、被害を最小限に抑えることができます。
4.4 法的手続きを適切に進められる
訴訟、仮処分、輸出入差止の申立てなど、どの手続きが最適かを判断し、スムーズに進めることができます。
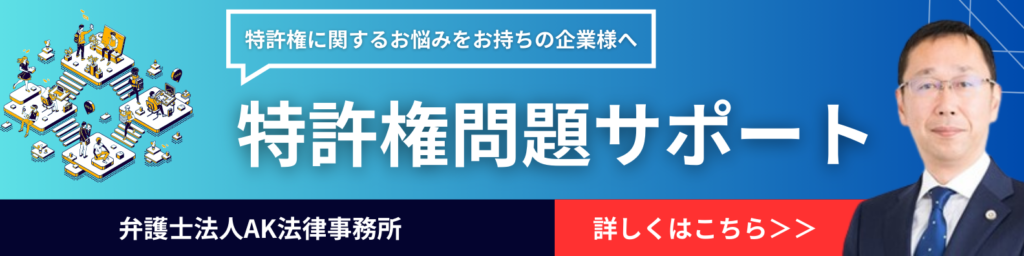
5 特許権侵害に関するトラブルは当事務所にご相談ください
当事務所では、特許権侵害に関する相談を幅広く受け付けています。
当事務所のサポート内容
- 侵害の有無に関する法的アドバイス
- 警告書の作成
- 交渉の支援
- 訴訟対応、差止請求の実施
- 特許権保護戦略の策定
特許権侵害の問題は、迅速な対応が求められます。まずはお気軽にご相談ください。




