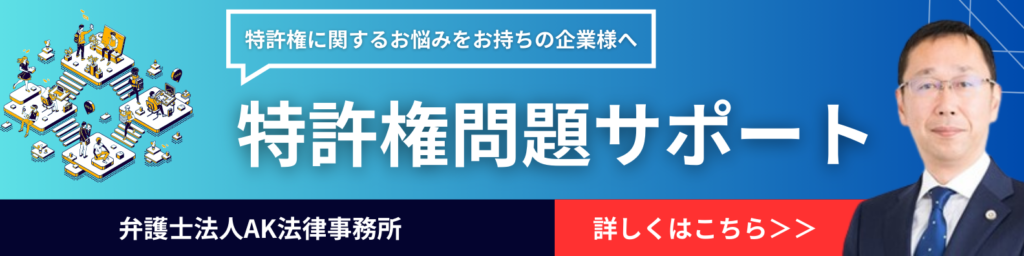1 特許権侵害とは
1.1 特許権侵害の3つの要件
特許法は「特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する」と定めています(68条)。
よって、特許権者の許可を得ることなく、業として特許発明を実施すると特許権侵害となります。
すなわち、特許権侵害となる要件は次の3つです。
特許権侵害の3つの要件
- 特許権が存在すること
- 特許発明を実施すること
- 「業として」の実施であること
これらの3つの要件の詳細については、のちほど解説します。
1.2 特許権侵害をするとどうなるか
特許権者は、侵害者に対して、特許権の侵害行為の停止や予防を請求することができます。
また、特許権侵害は民法上の不法行為となりますので、特許権者は侵害者に対して損害賠償請求をすることもできます。
さらに、特許発明を実施する場合、本来であれば特許権者に対してライセンス料金を支払って実施許諾を受ける必要があります。しかし、特許権侵害者はその支払いをすることなく特許発明を実施していますので、ライセンス料金の支払いを免れるという不当な利益を得ているといえます。よって、特許権者は侵害者に対し不当利得返還請求をすることができます。
これらに加えて、特許権者は侵害者に対し、業務上の信用を回復するのに必要な措置(信用回復措置)を請求することもできます。
なお、特許権侵害には刑事罰もあります。
特許権侵害者に対する制裁
- 侵害行為差止め: 侵害行為の中止や侵害品の廃棄など
- 損害賠償: 権利侵害による損害の補填
- 信用回復措置: 業務上の信用を回復するのに必要な措置
- 刑事罰: 懲役、罰金等
2 特許権が有効に存在していること
特許権侵害が成立するためには、上記の3つの要件を満たす必要があります。
まず、権利が有効に存在していることが大前提となります。
2.1 特許権が権利化されていること
特許権侵害の発生には、侵害される権利が存在していることが大前提となります。よって、侵害行為時に特許権が有効に存在している(存在していた)ことが必要です。
次の図にあるように、特許出願は特許庁での審査を通過すると特許査定され、特許料の納付によって設定登録され、特許権が発生します。したがって、出願公開段階であったり、特許料を支払っていない場合には権利が発生していませんので、当然特許権侵害も発生しません。
2.2 特許が無効・取消しになっていないこと
特許の設定登録後であっても、特許異議申立てによる取消決定や無効審判による無効審決が確定している場合は、特許権ははじめから無かったことになります。
特許権ははじめから(遡及的に)存在しなかったことになりますので、特許が無効・取消しになった場合には侵害も発生しません。
2.3 権利が消滅していないこと
なお、特許後の維持費用の不納や特許権の放棄によって権利が消滅している場合もあります。
ただし、これらの場合には特許権は消滅時まで存在していたことになります。よって、特許権が存在していた期間について、過去分の損害賠償請求をすることは可能です。
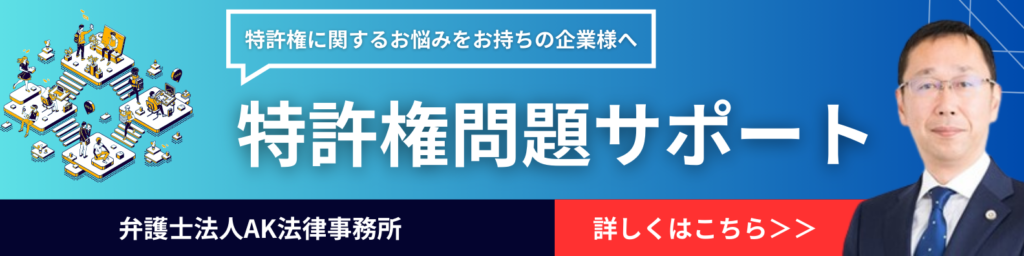
3 特許発明を実施していること
3.1 特許発明の実施とは
権利者に無断で特許発明を実施すると特許権侵害となります。
どのような行為が「特許発明の実施」に当たるかは特許法に定められており、発明のカテゴリー(物の発明、方法の発明、物の生産方法の発明)によって異なります。
大まかにいうと、物の発明の場合、物の生産、使用、譲渡、譲渡の申し出など、方法の発明の場合は方法の使用、物の生産方法の発明の場合には、生産方法の使用、生産した物の使用、譲渡などです。
どのような行為が特許発明の実施に当たるかは、次の記事もご覧下さい。
3.2 発明の技術的範囲とは
侵害製品や方法が特許発明の技術的範囲に属している場合にはじめて「特許発明の実施」となります。
特許発明の技術的範囲は特許公報の「特許請求の範囲」に記載されています。侵害製品や方法が特許請求の範囲に記載されている要件を全て充足する場合に、特許発明の技術的範囲に属するということができます。よって、侵害製品や方法が特許請求の範囲に記載されている要件を1つでも満たさない場合には、原則的には特許権侵害とはなりません。
この特許請求の範囲に記載されている要件を発明の「構成要件」といい、侵害製品等がこれを充足することを「構成要件充足性」などということがあります。
特許請求の範囲は、発明の内容を言葉や化学式で表現したものですから、物や方法がその技術的範囲に含まれるか否かの判断は、法律と技術の両方から検討して文言解釈をする必要があります。特許出願明細書の発明の詳細な説明や、特許の審査経過における出願人の言動なども参酌して、文言解釈を行います。
4 「業として」実施していること
特許権者に無断で特許発明を「業として」実施した場合に、特許権侵害となります。
「業として」の実施からは、家庭内実施や個人的な実施は排除されます。しかし、広く事業に関連していれば「業としての実施」あたるためその範囲は広く、反復性がなかったり、営利目的が無い場合であっても「業として」の実施に該当します。
5 間接侵害・均等侵害について
上記のような侵害行為に当たらない場合であっても、そのような侵害行為を引き起こす蓋然性の高い、一定の予備的・幇助的行為は侵害行為とみなされます。そのような行為は間接侵害行為とよばれており、特許法に類型化されています。
また、文言上は発明の技術的範囲に属さない場合であっても、一定の要件を充足する場合には、特許請求の範囲の文言解釈として特許発明と「均等」であるとして、例外的に侵害が認められることがあります。そのような解釈は「均等論」とよばれており、判例上認められている解釈です。
「均等論」は米国の判例法上発展した考え方であり「Doctrine of Equivalence」の訳です。Equivalenceに「均等」という訳語が与えられています。
しかし、AとBがEquivalent、すなわち実質的に同じようなものであることを、日本語の表現として「AとBが均等」ということはあまりないように思います。英和辞書にも、Equivalenceの訳語が「均等」とされているものは見たことありません。
訳語に忠実であるなら「等価」「同価」「実質的同一」などというべきかもしれませんが、上記最高裁判例の前から学説上では「均等論」という語が定着しており、最高裁も「均等」という語を用いています。これは一種の法律業界の特殊用語(Legal Jargon)なのかもしれません。
6 特許権を侵害しない例外について
形式的には上記の侵害行為にあたるような場合であっても、例外的に特許権の効力が及ばない場合があります。特許法は特許権の効力が及ばない場合を規定しています。また、特許法の規定や判例法理によって、特許権侵害とならない例外的な場合もあります。
特許権が及ばない場合
- 試験又は研究に当たる行為
- 日本国内を通過するに過ぎない航空機等、及び、これらに使用する物
- 特許出願の時から日本国内にある物
- 一定の医薬発明について、処方箋によって調剤する医薬品
また、次のような場合も特許権侵害とはなりません。
特許権侵害とならない場合
- 先使用権、中用権、裁定実施権などの法定通常実施権がある場合
- 特許に無効理由がある場合
- 特許権が消尽している場合
- 特許権者からの実施許諾がある場合
- 正規品の並行輸入の場合
7 侵害時の対応について
7.1 チェックリスト
特許権侵害の有無を判断するには上記の事項をそれぞれ確認する必要があります。具体的には次の通りです。
特許権侵害のチェック項目
- 特許権が有効に存在しているか
- 特許料が支払われているか
- 放棄されていないか
- 無効・取消しになっていないか
- 侵害態様の確認
- 侵害製品の販売等
- 方法の使用
- 侵害物件、方法が特許発明の技術的範囲に属するか
- クレームチャートの作成
- クレーム解釈(出願明細書、審査経過の参酌)
- 「業として」の実施に当たるか
- 間接侵害・均等侵害に当たるか
- 特許権が及ばない場合に当たらないか
- 試験又は研究に当たる行為
- 日本国内を通過するに過ぎない航空機等、及び、これらに使用する物
- 特許出願の時から日本国内にある物
- 一定の医薬発明について、処方箋によって調剤する医薬品
- 特許権侵害とならない事由がないか
- 先使用権
- 法定通常実施権
- 無効理由
- 特許権の消尽
- 実施許諾
7.1 特許権が有効に存在しているか
特許権侵害が疑われる場合には、まず権利が有効に存在しているかどうかを確認することが重要です。
具体的には、特許権の現況は、特許情報プラットフォーム「J-PlatPat」よりオンラインで確認することもできます。オンラインの情報には掲載までの時差がありますから、特許庁より特許登録原簿を取り寄せて閲覧するとより確実です。
7.2 侵害態様の確認・保全
特許発明の種類によって侵害となる実施態様が異なります。
侵害製品の販売、販売申し出、輸入などが問題となる場合には、これらの事実の有無を調査し、証拠化しておくのが望ましいです。具体的には、侵害製品の店舗での販売態様、価格などの写真撮影、カタログ等の取引書類の収集、販売ウェブサイトをプリントアウトするなどして証拠保全しておくのが望ましいです。
方法の発明が問題となる場合には時的要素が絡んできます、実際に方法が使用されている場面を撮影などできればよいですが、現実的には困難なことが多いです。よって、方法の使用による結果に着目したり、方法の使用の申し出、例えばウェブサイトでのサービス提供の文言などから推測せざるを得ません。
7.3 侵害物件、方法が特許発明の技術的範囲に属するか
侵害物件や方法が特許発明の技術的範囲に属しない場合には特許権侵害となりませんので、属否を確認する必要があります。
多くの場合、特許請求の範囲を構成要件に分説して、実施する物、方法、製造方法が構成要件を全て充足するかどうかを検討します。この検討結果を表にしたものは「クレームチャート」と呼ばれています。特許権侵害が疑われる場合には、クレームチャートを作成しておくと便利です。
クレームチャートの作成には、特許請求の範囲の文言の解釈が欠かせません。これには、特許に関する法的な知識と、技術的な知識の両方が求められます。
7.4 業としての実施か
業としての実施に当たるかは、家庭内実施や個人的な実施かどうかをチェックすることになります。事業者による実施の場合、通常は業としての実施に当たります。
事業者が関与していても、最終的な実施者が業としての実施をしていない場合があります。例えば、「物」の特許発明の場合に、その「物」の組み立てキットを販売して、「物」の製造自体は家庭内で行われるような場合です。そのような場合には、次項の間接侵害の有無を検討することになります。
7.5 間接侵害・均等侵害に当たるか
間接侵害・均等侵害の成否については、特許請求の範囲を文言解釈した上で、特許法の条文や裁判例の規範に照らして判断をすることになります。
7.6 特許権を侵害しない例外に当たるか
上述の通り、特許権侵害が成立しない例外的な事由は様々なものがあります。
特許権侵害を主張する側でしたら、侵害者の行為がこれらの全ての例外に当たらないことを確認します。他方、特許権侵害を疑われている側でしたら、これらの例外のうちどれか1つでも該当すれば大丈夫ということになります。
特に、先使用権や無効理由の存在については、沢山の資料を収集することが必要となってきます。紛争が本格化してから慌てないよう、余裕を持った調査が望ましいです。
8 弁護士・弁理士に相談しましょう
上記の通り、特許権侵害の検討には、専門的・技術的な知識が必要となってきます。
特許権侵害が疑われる場合には、早めに弁護士・弁理士といった専門家に相談することをお勧めします。